ひらりと手渡されたのは、何の変哲もない紙切れだった。
「何だこれは。」
渡してきたリィンは、ええと、と頬を引っかく。
「スープのレシピだよ。バリアハートの実習の時に貰ったんだ。
二日目朝の課題だったからユーシス居なかっただろう?俺の分は写したから、こっちはユーシスにと思って。」
「……なぜ俺に?」
紙切れをつまんで聞くと、リィンはああ、と頷いた。
「これ、ハモンドオーナーから貰ったものだからさ。」
「ほう?」
思わず中身に目が行く。クリームチャウダーと銘打ったレシピには、確かにそれらしい材料が並んでいた。リィンはその上からかぶせるように先を続ける。
「実習のときはこれにキュアハーブと魔獣の油脂が入ってたんだけどな。懐かしのメニューを作りたいからって。」
「ああ……。」
確かにそれは聞いていた。自分は不参加だったが、課題の内容に食材集めがあったのだ。確か教会で分けてもらったとか、街道でわざわざ魔獣から手に入れたとか言っていた気がする。
しかし、キュアハーブを使うスープ料理には覚えがあった。それを加味してもう一度レシピを見ると、どうやら思った通りで間違いないらしい。
あのスープだ。
これにハーブを混ぜるまでは記憶があった。幼い日のものだから完全にうろなのだが、まあ間違っては居ない気もする。
間違っては居ない、のだが。
「……しかし、これを俺が持っていて何になる?」
レシピをなぞっていた視線をリィンに向けると、リィンは面食らったようにこちらを見た。しかし、すぐに肩をすくめて首を振る。
「それはわからないけどさ。捨てるのはあんまりだし、ハモンドオーナーから貰ったって事考えたら、俺が持っているよりはいいんじゃないか?
ほら、気が向いたら作ってみるとか。」
「作るだと?」
鸚鵡返しに聞き返すと、リィンはそうさと頷いた。
「実際やるかどうかはともかく、それが一番の有効活用だろ?折角シェフのレシピを貰ったんだし。」
自分でこれを作る、と。その発想はなかった。しかし、強硬に断るのも何か違う気がする。
「……フン……まあ受け取ってやろう。」
メモを持った手を下ろすと、リィンは心なしか満足げに頷いた。
ああ、そうしてくれ、と。
……そしてこの紙はいまここにある。
材料はミルクにチーズにポテトに白身と殻。後は確か、ハーブをいくらか。レポートを確認したら取りにいったものはわかるだろう。ことさら高級な食材を使っていたわけではないし、揃えようと思えばすぐ揃う。味付けは、このレシピの通りにすればまず問題ないはずだ。
そこまで思考を廻らせて、自分がこれを作るつもりになっている事に気が付いた。
料理などまともにした事もないのに、何を考えているのだと肩をすくめる。ただ、馬鹿馬鹿しいと思うのに、レシピを放り出すことはできなかった。
昔よく母親が作ってくれていた、自他共に認める好物だった。レシピを綴るのは、懐かしさすら覚える伯父の筆跡。作り方も手順からみじん切りの仕方からと随分と事細かに説明してあって、初心者に向けて書いたものとわかる。
そう、初心者にだ。
なんとなくオーナーの顔が見えるようで、思わず顔が緩んだ。
依頼の取りまとめは兄がやっていた、という事はオーナーはこれが誰の仕事になるかは無論知っていただろう。そして、本来ならこの依頼は自分もやるはずだったのだ。
……誰に向けたものかなんて、良く考えなくても自明だった。オーナーは多分、この味を自分に伝えたかったのだろう。もしかしたら作ってみて欲しいとでも思ったのだろうか。だとしたら随分な挑戦である。
しかしそれならば、受けて立つまでだった。そして、受けて立つからには勝利せねばならないのだ。
時計を眺めて、頭の中のカレンダーをめくる。予定も詰まっている事を考えると、決行は早いほうがいいようだった。
そして今、材料は必要以上に揃い、今目の前に並んでいた。
材料を買い求めに行った先では揃って驚かれ、ハーブを貰いに行った先の教会ではシスターにはまあまあと妙な感嘆詞を連発され、おまけと称して余分に貰ってしまったのだ。故郷に居た時の下にも置かない扱いとは違うのだが、ほとんど珍獣扱いである。
どっさり、という表現の似合う材料を眺めて一息。まずはレシピを汚れなさそうなところに置いて、手順の確認から始めることにする。
最初は殻でスープを取るところから。そしてその間に材料をみじん切りにする、と。
『煮込む前にハーブを半分、煮込み終わってもう半分。油は浮かないように、だけどコクが消えないように。』
幼い日の記憶を引っ張り出して、記憶の中の母の声と所作を反芻しながら手順を進める。
クセのあるハーブだって、塩で揉み、湯に通して水に曝し、刻んで処理すればクセは抜ける。それでも香りの抜けないハーブはなんだか母のようだなと今更ながらに思った。あまり台所には入れてもらえなかったが、料理をする母親がとても楽しそうだったのは確かで、その様子が幼心に安心できて、……だからなんとなく覚えていたのだ。
気がつけば一時間は軽く経過していた。
コトコトと煮込まれているスープからは、馴染みのある香りが漂っている。ある程度の片付けもできたし、そろそろ食べられるだろうか。
味見、と思って玉杓子を鍋から引っ張り出すと、白くて少しトロみのついたスープが滴り落ちた。それにそのまま口をつけるのもはばかられて、小皿を出す。そして、小さな皿に気持ちだけ入れたスープを少しだけ口に含んだ。
芯から温まるハーブの香りと共に、口中にスープの味が広がる。
レストランのシェフが作ってくれる物よりは幾段落ちるが、多分こちらが母の味には近いという確信があった。素朴で、暖かくて、……涙が出るくらい懐かしい味。
「……母さん……。」
会えなくなってもう何年も経つ母親が、ふと笑いかけてくれたような気がして、思わず声が漏れる。くつくつことこととスープの鳴る音が、何かしら答えてくれているような気すらして……はたと我に返った。
ぼうっと浸っている頭を振って、気持ちを切り替える。
……基本の味は悪くない。もう少し塩を入れて、チーズを掛ければ完成だ。
そう思って、調味料に手を伸ばす……と、何か、さっきまでなかったものに気がついた。
食堂のカウンターの向こうから、じっとこちらを見ている奴がいる。ぎょっとして目をやると、銀色の髪の毛がひょこっと揺れて、薄緑の目が瞬いた。
「……あ。気がついた。」
「な……!!!!」
続きは声にならなかった。今の今まで気配などなかった。いや、全然気付かなかったのだ。
「美味しそうな匂いがしてたから。」
足音もなくカウンターのこちら側に来られても、どう対応すればいいのか分からない。
「随分一杯作ったんだね。」
鍋を覗き込んだ瞳は、そのままこちらを向く。
じいっと目があって、それは逸らされず……そして、その間に心も少しだけ落ち着きを取り戻した。
「……フィー。お前、いつからそこにいた?」
目を逸らさずに言うと、フィーもじっとこちらを見上げてくる。
「……母さん、のあたりから。」
額を押さえたいのと即刻フィーの記憶を消し去りたいのをぐぐっと我慢して、睨みつける。
「……絶対他言するなよ。」
言うと、フィーの目はするっとスープに逸れた。
「……これ、食べちゃ駄目?」
「他言しないと誓うなら好きに食べて構わん。」
「……えー……」
不服そうなフィーをぎっと睨みつけると、フィーは降参、というように肩をすくめた。
「めんどいけど仕方ないか。……絶対言わない。約束する。」
「ならいい。皿でもなんでも持ってこい。」
言うと、フィーはまたぴょこっと顔を上げる。
「ありがと。……パンあったかな。」
ふいっと踵を返し、音もなく台所を抜けていくその姿は少し浮ついて見えた。
「……パンか。」
ふむ、と考える。確かに夕飯にするなら主食くらいは必要だろう。普段は外食で済ませるため、今部屋にパンなど置いていないのだが。
買いに行くか。そう決めて、スープの火を止めた。確か雑貨屋に一緒に置いてあった気がする。
食堂から出ると、駆け下りてきたフィーと鉢合わせた。
「ユーシス、どこいくの?」
「ちょっと出てくる。スープは好きに食べていい。だから、他の奴が帰ってきても何も言うなよ。」
「ん、了解。」
ぴょこぴょこと食堂に入っていくフィーの手にはそういえば何もなかったが、もう関知しないことにする。
外に出ると既に街は夕暮れに染まりかかっていた。
*****
「ただいま、っと……ん?」
開け放った扉からは、なんとも胃袋を直撃するようないい匂いが流れてきていた。思わず立ち止まると、背中にどんっと誰かの頭がぶつかる。
「ったあ。マキアス、いきなり立ち止まらないでよ。」
「ああ、悪い。」
慌てて場所を空けると、もう、と文句を言いながらエリオットも中に入ってきた。後ろからはガイウスも一緒である。
帰りの校内で行きあって、三人でそのまま一緒に帰って来たのだ。
「……あれ?いい匂い。誰かな。」
「……ふむ……何か、香草のような匂いだな。」
くんくん、と鼻はいい匂いの震源地へ向く。その先にあるのは食堂だ。ただ、この香りには何かとても思い当たるものがあった。
「何か、覚えがあるんだが……。」
なんだったか、と食堂のドアを開ける。と、ロビー一杯にハーブとミルクのいい匂いが広がった。すきっ腹には非常に刺激的な香りに、腹の虫がうずく。
中に居たのはフィーだった。
「……あ。帰って来たんだ。おかえり。」
食堂の片隅でスープを口に入れながら顔を上げる。
「ただいま。……これ、フィーが作ったの?」
エリオットが尋ねると、フィーは首を横に振った。
「ううん。
でも、好きに食べていいって言われたから食べてる。」
誰がそんな事を言ったのだろう。聞こうとする前に、フィーはことんと首を傾げる。
「……3人とも、食べる?」
言葉と共に、抗えない美味しい香りが思い切り鼻腔をくすぐった気がした。即頷きたいのをぐっと耐えて聞いてみる。
「……誰が作ったんだ?」
しかし、それに対する答えはなかった。
「好きに食べていいらしいから。」
待ってて。
カタンと匙を置くと、すぐに新しい皿が三枚出てくる。そして問答無用でスープが注ぎ分けられ、食卓に並んだ。
「ん。」
どうぞ、と差し出されて三人顔を見合わせる。
「……いいのだろうか?」
胃袋の指示に従えば、すぐにでもこれをがっつきたい所だったが、それでは何か申し訳ないような気がしなくもない。しかし、目の前のスープを放置すれば冷えていく一方だ。それはそれでとても勿体無い。
「とりあえず、冷めるよね。」
「うむ。それは勿体無いな。」
ガイウスとエリオットはそれでまとまったらしい。そして自分も、もうこの香りには抗えなかった。
こほん、と一つ咳払いをする。
「……礼はする事にしよう。部屋にクラッカーか何かあった気がするし、持って来るか。」
「あ、それなら僕も部屋にビスケットがあったっけ。」
「ふむ。それなら俺は野菜でも提供しよう。」
食べる前に取りに行こうと、ばたばたと踵を返すと、フィーもすっと付いてくる。
「どうした?」
聞くと、フィーは振り向きざまにするっと間を抜けていった。
「私も何か持ってくる。」
「……うむ、いい傾向だな。」
微笑ましげに見守るガイウスの後ろから、そうだな、と頷く。
「少し変わってきたよね。とっつきやすくなったっていうか。」
「まあ、いい事だろう。」
そんな事を言いながら、三人は階段を駆け上がった。
コンビーフの缶詰を薄く切っただけのもの。
葉野菜を千切っただけのサラダ。
クラッカーとビスケットが申し訳程度に皿に並んだもの。
そんな質素な持ち寄りでも、食卓は随分賑やかになった。
冷めないうちに、と挨拶もそこそこにスープに取り掛かる。
「……へえ、これ温まるね。」
「ああ。何か、風邪に効きそうな味だな。」
美味しいね。そうだな。そんな他愛ない会話をしている二人をよそに、マキアスは一人一匙目を口にしたまま考え込んでいた。
覚えのある香りだと思っていたが、味にも覚えがある。ハーブの効いたクラムチャウダーは、ついこの間バリアハートで食べたものだ。ただ、レシピを貰ったのは見ていたが、内容はこれとは違うと聞いていた。これは特別製だからベースのレシピを教えると、確かにあのシェフは言っていたのだ。
「……ふむ。フィー、これは誰が作ったんだ?」
返事はない。フィーはもくもくとスープをすくい、ビスケットを齧っている。
「フィー、無視するな。」
少し語気を強めるが、フィーはちらっとこちらを見たきり、またスープに向いてしまった。
「……エマくんか、リィンか?」
やはりノーコメントである。しかし、この予測は恐らくそう間違っては居ない、と判断した。
それなら美味しいうちに食べて、きっちり礼をするのがよさそうな気がする。
「マキアス、心当たりでもあったの?」
エリオットに問われて、ああ、と頷く。
「これはこの間の実習で食べた物なんだ。つまりこの味を知ってるのは、僕たちA班だけということになる。
で、フィーでなくて僕でないなら、残りはエマくんかリィンだと言う事だろう?」
証明終了、と野菜の方に手を伸ばすと、ガイウスがふむ、と頷いた。
「確か、ユーシスも居たのではないか?」
「アイツがわざわざ自分で料理を作ると思うか?」
99%ないと首を振るが、ガイウスはまだ疑問があるらしい。
「可能性は捨てられないと思うが。」
「それでも限りなく低いさ。こんなに美味しいスープを、普段料理しない奴に作られてたまるか。」
言っているうちに、外からまた賑やかな声が聞えてきた。
ただいま、とか、美味しい匂いがするだとか、誰かいるようだとか。
この声は、と思っているうちに食堂の扉が開いた。
「ふむ、匂いの元はやはりここだったか。」
「へえ、随分美味しそうじゃない。どうしたの?」
連れ立って帰って来たのは、アリサとラウラである。
「あ、おかえり。」
フィーはそう言うと、ぱたんと席をたった。向かう先は食器棚だったようで、またかちゃかちゃと音がする。それをそっと見やってから、エリオットは二人に向き直った。
「お帰り、二人とも。何か、フィーが好きに食べていいからって。」
「まあ、成り行きで、頂いているところだ。」
多少バツは悪いが、一応現状を説明してみる。
「フィーは誰が作ったか言ってくれないのだが、かなり美味だぞ。」
「ちなみにこっちのビスケットとかは僕たちのだから、それこそ好きに食べちゃっていいけど。」
エリオットが言うと、アリサとラウラは顔を見合わせた。
「……この匂い、確かに部活帰りのお腹にはたまらないんだけど。」
「しかし、食べていいものなのだろうか?」
「……ん、どうぞ。」
気がつくと、フィーが二人の前でスープ入りのお皿を差し出していた。いつの間に温めなおしたのかほかほかと湯気が立っていて、また美味しそうな匂いをさせている。
「フィー、これは誰から?」
アリサが聞くと、フィーは食堂の外に顔を向けた。
「……そろそろ帰ってくるはずなんだけど。」
「なぜ言わぬ?」
ラウラに問われても、フィーは困ったように目を戻すだけである。
「……スープ、冷めるよ。」
疑問顔にフィーの言葉が入り込んで、二人は顔を見合わせた。
「……お礼、すればいいわよね。……というかもう抗えないわ。」
「……うむ。食べていいのならば美味しいうちに頂くのが礼儀だろう。……私もこの匂いには抗えそうにない。」
うん、と二人で頷いて、フィーに向き直る。
「頂こう。私からも何か持ってくるゆえ、食卓に置いておいてくれないか?」
「そうね、私も何か持ってきましょう。フィー、ありがとう。」
「うん。わかった。」
こくり、と頷いて、食卓に皿がまた増えた。
軽く焼けたウィンナーとざくざくと切られた果物が置かれると、食卓はさらに賑やかになった。
「随分豪勢になったよね。」
「ふむ、こういうのも楽しいものだな。」
エリオットが果物をつまめば、ラウラもクラッカーをスープにつける。
「作ったのって、今居ない三人の誰かよね。本当に美味しいわ。ふふ、感謝しないとね。」
「ああ、いい風の導きだったようだ。」
アリサがビスケットを齧りながら笑うと、ガイウスもウィンナーをつまみながら頷いた。
「しかし、どっちだろうなあ。エマくんかリィンか。」
コンビーフをつまみながら言うと、フィーはサラダを齧りながらボソリと言う。
「誰であろうと、やる事は変わらないよ。」
「ま、それもそうか。誠心誠意、感謝するだけの話だ。」
言うと、フィーはするっと視線を逸らした。
「フィー?」
「……ん、なんでもない。」
「そうか?」
首をかしげたところで、玄関の方からまた声が聞えてきた。いい匂いだの、凄いだのいう声は、男子生徒の声二種と女子生徒の声一種。
「帰って来たか。」
「三人一緒みたいね。」
食堂の入り口のほうに目をやると、すぐに扉が開いた。立っているのは想像通り、リィンとエマとユーシスである。各々に買い物袋を抱えた姿からすると、今まで買出しにいっていたらしい。
「おかえりー。」
「その、ありがたく頂いているわ。」
「ああ、美味しく頂いている。」
口々に声を掛けるが、戸口の三人はただいまの一言もなく、唖然とした顔で固まっている。
そして一秒。
「おい、これはどういうことだ?」
ユーシスがゆっくりと口を開いた。
そのきつめの言葉と目線の先に、皆の目が行く。その先ではフィーがすましてスープを飲んでいた。
「……好きに食べてみた。」
淡々とした言葉が無造作に放り投げられる。
それだけで、おおよその事は知れた。思わず傾いたスプーンから滴り落ちた白い雫が、皿の中にぽてりと一輪の波紋を描く。
「……ユーシスだったんだ……。」
うわぁ、と困惑も露にエリオットが呟いた。
「行き違いがあったのか?」
リィンが言うと、ユーシスはぎっとフィーを睨みつける。
「行き違い?違うな。これはどう考えても確信犯だろう。」
視線の先のフィーは、相変わらずのすまし顔だ。
「フィー、まさかとは思うけど、ユーシスに許可を取っていなかったの?」
アリサが眉をひそめるが、フィーは、その先でううん、と首を横に振った。
「ユーシスの事黙っているなら、好きに食べていい、って言われた。」
しれっとスープをすくう姿は、まさに蛙の面になんとやらといった風情である。
「なるほど、口止めされていたのか。」
ラウラが息をついた。フィーが頑強に作者の名前を言わなかったのはこのせいらしい。しかしそんな事をしなければこの事態は防げただろうというのは皆一致するところで、若干気まずい視線がユーシスに向く。
「……その、食べてはいけなかったのだろうか?」
ガイウスが尋ねると、ぎりぎりとしていたユーシスも、どうしようもないと悟ったか額を押さえてため息をついた。
「いや、遠慮はいらん。別に皆に食べさせたくないなどとつまらぬ事を言う気は毛頭ない。
ただ、こうなるとは思っても居なかったというだけだ。理解力のない奴に好きに食べろといったのは俺の落ち度だがな。
フィー、一応聞くが、まだ残っているんだろうな?」
言うと、フィーはこくりと頷いた。
「ん。エマとリィンと一緒に食べてもまだあると思う。」
ていうか、ユーシス作りすぎ。
ぼそ、という言葉に、ユーシスは軽く鼻を鳴らす。
「そういうわけだ。準備してやるから食べてみるといい。」
言葉は隣で唖然と立っていたエマとリィンに向けられている。
「ええと、いいんでしょうか?」
「ああ、構わん。お前たちも遠慮などしなくていい。」
あちらとこちらと声を掛けながら、ユーシスは買出しの荷物を片手に台所の方に行ってしまった。
「ええと……」
がちゃがちゃと皿を出す音の中、リィンとエマが顔を見合わせる。
「ユーシスもああ言っているし、席に着いていいと思うぞ。」
ガイウスが声を掛けると、エリオットも続けた。
「リィン、エマ、そこら辺のビスケットとか食べていいよ。皆で持ってきた奴だから。」
「うん。こういうのは皆で食べた方が美味しいし。」
口々に声を掛けると、やっと頭が動き出したらしい。
「あー、俺も何か提供するかな。」
「そ、そうですね。私も何か冷蔵庫にあったかも……」
二人もぱたぱたと台所に向かっていった。
食卓にはスープが3皿増え、ポテトサラダとパンとチーズが増えて、さらに賑やかになった。
「本当に美味しいですね。」
「へぇ、やるなぁユーシス。」
ポテトサラダとチーズの提供者はそれぞれほくほくとスープを口に運ぶ。
「フン、当然だ。」
作成者はスプーン片手に傲然と言い放つが、それは少しだけ嬉しそうにも見えた。
「本当に、随分意外な特技をもっていたのだな。
いや、馬鹿にしているわけではないんだが。……むしろ羨ましいのだが。」
パンにスープを吸わせながらラウラが言うと、ふい、とユーシスの目線が逸れる。
「別に……手順どおりに作っただけだ。」
「本当、教えてもらいたいくらい。温まるわよね。」
アリサの素直な賛辞に、フンと鼻を鳴らしているのも流石にテレが見え隠れしている。
「しかし、誰が言い出したかは知らんが、随分と賑やかになったものだな。」
話を逸らすようにユーシスが言うと、フィーがしれっと応じた。
「スープもらうならお礼くらいしようって。言いだしっぺはマキアス。」
全部の視線がこちらに飛んでくる。
「フン、随分と気のきく事だ。貴族風情の料理など食べられたものではなかったのではないか?」
挑発の色もあからさまな言葉に、ふん、と鼻を鳴らした。
「ああ、お前が作ったと知ってから味が五段は落ちたな。だが、貰った食べ物にはそれ相応の礼をするものだろう、作者が例えお前でもな。」
知っていたら食べていなかったのは間違いのないところだが、可能性を排除していたのは自分の落ち度でもある。
そもそも母親の味だと言われていたし、好物だとも聞いていたし、レシピはリィンあたりが渡したのだろう。そしてリィンからレシピを貰ったとすれば、作ってみようと思い立ってもそこまで不自然ではないのだ。
「ほう?お前にしては随分と殊勝な事を言う。」
挑発の色は消えていない。しかし、食卓でいがみ合うのはどうかという理性はまだ最後の一欠けら程度は残っていた。一息ついてスープをすすって見せる。
「不味くは無かったからな。それともお前は母親の味を貶されたかったのか?」
「なっ……!!」
チラリと見たユーシスの顔色は見事に変わっていた。何でお前がそれを知っている、とあの鉄面皮が冗談のようにありありと書いてある。
「リィンから聞かなかったのか?バリアハートで大体聞いたぞ。お前の好物だということもな。」
「……なるほど、母の味だったのか。」
へぇ、と興味深げな先月のB班組にそういうことだ、と頷いて見せる。
「僕にだって攻撃先を選ぶくらいの分別はある。」
「っ……。」
絶句しているユーシスがとてもとても新鮮だった。
「……これはマキアスの勝ちだな。」
リィンが小声で肩をすくめる。
「一本勝ちね、珍しく。」
「アリサさん、そういう言い方をするものでは。」
くすくすと笑ってアリサが言うとエマが慌ててたしなめた。その向こうで、フィーがうんうんと頷く。
「マキアス、成長した。」
小さな手が偉い偉い、と空中を撫でる。が、その手は空中で振り払った。
「フィー、君は少し反省したまえ。そもそもなんでこんな事をしたんだ。これじゃ完全にだまし討ちだぞ。」
礼をしなくては、と言った時に目を逸らした理由だって今なら自明すぎて、その時点で気付いていればという気持ちは大きい。
が、フィーはするっと目を逸らしただけだった。
「フィー、聞えないフリをするなっ!」
「……知らない。」
それを他所に、ガイウスが感慨深げに頷く。
「なんというか、四月のアレが嘘のようだな。」
「あはは、本当。」
「確かになんと言うか……とても感慨深いですね。」
エマまでそう息をついた。とても釈然としない。が、ギリギリと額を押さえているユーシスはもっと釈然としないらしい。
「おい。」
「ユーシス、折角のスープが冷めるよ。」
しかし、言葉はフィーからの声でさっくりさえぎられた。その上にラウラの言葉が追い討ちを掛ける。
「うむ、勝ち負けはともかく、食べ物は美味しいうちに食べるものだぞ。」
事実と正論の前には矛を収めるしか選択肢は残らない。
「……全く。何でこうなったんだ。」
ぶすっとした言葉は、ユーシスは認めないだろうが事実上の敗北宣言だった。
それに、しれっとした声が応じる。
「決まってる。
ご飯は皆で食べたほうが美味しい。」
フィーは、そう言ってクラッカーをパリンと齧る。
「そういう」
「なるほど、真理だな。」
「そういえばこんな機会も無かったしね。」
文句の前に頷く外野は楽しげで、文句の挟める隙間も消えた。それに毒気を抜かれたか、ユーシスも一つ息をついて食卓に手を伸ばす。
「もういい。俺にもそのサラダを寄越せ。……全く、本当に度し難いなこのクラスは……!」
ぶつぶつ言う文句に、食卓から和やかな笑い声が上がった。
しばらくすると教官も帰ってきて、食卓はますます賑やかになった。
食べ物は質素で取り分けられてすら居ないが、実家に居た時より遥かに美味しく感じる。
なんとなく、遠く忘れていたはずの温かな食卓を思い出した。ここにも同種の何かがあるのだろうか。
わいわいがやがやと食事時とは思えない賑やかさの中、ぼんやり思う。
……なるほど、こういうのも悪くない。
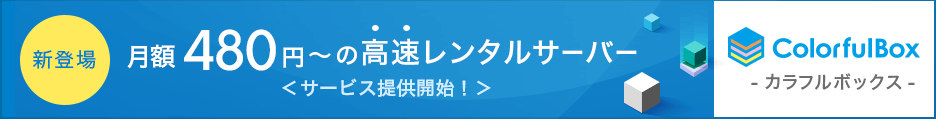






二週目、ステラガルデンにユーシスを連れ込むという暴挙を犯した結果、やっぱりこの人私の好きなタイプなんだなあとしみじみ思いました。ユーシスは本当プレイ開始30秒で一目惚れしたのですが、その時に大体なんとなく性格とか方向性とか想像ついてしまうくらい私の中では鉄板だったといいますか、期待を裏切らないというか本当想像通りすぎて自分の眼力に笑ってしまったといいますか。
素直に眼鏡と漫才やってるのが好きです。絶対才能あると思います(お笑いの)が、フィーを扱いかねてる感じも好きだし、エマにだけは紳士なのも可笑しいし、アリサに対してつっけんどんなのも面白いなあと思ってたら、ガイウスやリィンに対しては素直だし、エリオットには勝ててないし、本当見てて飽きないなあと。
それはともかく、みんなでわいわいやってる7組が可愛くてその可愛さを欠片でもいいから書きたかったんでした。一発目から割とオールキャラできてそこそこ満足です。
お料理って、リィンが居ないとみんな作れないのかなと思ったけど、別にそんな事もないよね、と思いつつ。
シャロンさんが居たらこの話成立しないんですよね。